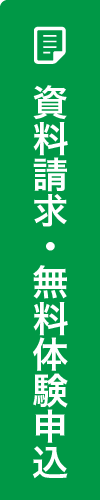算数がもっともっと好きになる!
本コースでは、開講以来、現在に至るまで、個々の目標及び設計カリキュラムに基づいて、双方向性の対話による生徒の可能性を伸ばす指導を続けており、その結果として、多数の上位進出者を輩出して参りました。
トライアル突破およびファイナル上位進出のため、階級別に、上位進出を目的に逆算されたプログラムにて指導します。
算数を通して、楽しんで学ぶうちに、考えることが好きになり、結果にもつながっていくという循環を作ります。
| 対象 | 算数オリンピック大会の上位進出を目指す小・中学生 算数を得意にして、中学受験を有利にしたいとお考えの方にオススメです。 |
|---|---|
| 場所 | 進学塾SOCRA&jr.浦和校 |
| 内容 | 少人数個別(1対6まで)にて各自の目標階級に応じた算数オリンピック対策を行います。 |
指導方針
難問に立ち向かうにあたって、正解という結果を出すことは非常に重要ですが、過程もそれ以上に重要です。
特に小学生が算数オリンピック大会の問題のような負荷の高い課題に取り組んだときには、本人の思考過程を大切にする指導が重要であると考えています。そのためのカギは、「適切なハードル設定」と「適切なコーチング」にあると考えております。
本トレーニングコースでは、1授業(90分)における受講者数を、きめ細かく目を配ることのできる人数(現行では6名以内)に制限しており、トレーナーと他の受講者とで互いに切磋琢磨する環境の中で、コミュニケーションをしながら、力を身につけていきます。
コース紹介
ベーシックコース
基本概念から習得していくコースです。
はじめて算数オリンピックに参加する予定の人、もう少し知識を身につけてから難問にチャレンジしたいと思っている人にオススメです。
マスターコース
過去問レベル演習を行うコースです。
ベーシックコースの内容では物足りないと思う人、少しでも多くの問題に出会って、算数の問題を考え抜きたいと思っている人、算数オリンピックに参加するだけでなく、上位進出を目指す人にオススメです。
キッズBEE向け(年長~小3)
- キッズBEEベーシックコース
- キッズBEEマスターコース
ジュニア算数オリンピック向け(~小5)
- ジュニア算数ベーシックコース
- ジュニア算数オリンピック マスターコース
算数オリンピック向け(~小6)
- 算数ベーシックコース
- 算数マスターコース