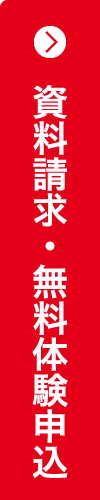SOCRAの国語
国語
課題文を正確に読み解くこと、そのために、説明文ならば、背景知識や語彙、慣用句、修辞技法などの知識分野の錬成と、文法や論理展開を踏まえた精読を行います。小説の場合には、登場人物の性格や境遇、時代背景や文化による価値観の異同などの与件に留意し、心情の推移をその契機となる出来事と合わせて仔細に検証し客観的に読むことを行います。
分析力を高めるために、問いに対するアプローチの定石を身に付けること、どんな設問に於いても原理原則を一貫して応用できるよう徹底して反復することです。問いを精査し、解答への要件を洗い出し、その全てを過不足なく満たすことが必要です。成否を問わず解へのプロセスを重視し、根拠が反証され得ないものか共に考えることを通して思考力を養います。
記述力を高めるために、「説明するとは何か。」という基本的な問いから初め、設問を定型に分類し、形式と内容の双方から解答を導きます。より洗練された記述を目指し、語彙力の形成に重点を置きます。言葉を自在に使いこなすことは、意味だけでなく、同意語、反意語、上位語、下位語など言葉の関係を意識した学習が必要です。単語から文へ、文から段落へ、段落から文章へと範囲を広げ、自分の言葉で換言する力を養いたいと考えています。
したがって、国語で求められる力は、文章を通して筆者が伝えようとする真意を汲み取る読解力、問いで求められている条件を整理し課題文と突合し判断する分析力、そして言葉を紡ぎ纏め上げる記述力ではないでしょうか。
国語の本質的な愉しみ方-
国語の本質的な愉しみ方とは、どんな問題を得意にするのかということではなく、文章の問い自体に探究心を持つことである。
文章を好きになること
どんな文章にも筆者の設定した、主題があり、問いがあり、答えがある。それは、評論文であれ、小説であれ当てはまることがある。評論文であれば、主題に対する筆者の主張、論点を読み取ることが求められよう。小説ならば、家族・恋愛・友情・成長など文章全体の主題があり、主人公は課題に直面し(問い)、言動を起こすこと(答え)を求められる。このように文章には筆者の設定したロジックや仕掛けがある。まずは、これらを発見することから始めてほしい。その中で文章に対する興味を少しでも多く抱いてほしいと思う。
問いの本質に答えること
問いに対して自分ならどのように答えるか、筆者に賛成なのか反対なのか、それはどのような点で、なぜなのかといった批判的な読み方を身につけたい。小説ならば、主人公になったつもりで追体験してほしい。そして自分ならどうするか、状況が変わったらどうなるか、などあれこれ思索してほしい。
言葉に興味を持つこと
語学である以上、語彙の習得を大いに計ってほしい。むやみに一日に何個を覚えるというより、わからない語彙を調べる習慣を身につけてほしい。
受験勉強の国語であることを割りきること
入試では、客観的に読むことが求められる。先生にそう指導されることもあるだろう。しかし、「客観的に」を「主観を交えずに」と理解しないでほしい。入試で求められる客観とは正しい主観を持つことなのである。そのため、正確な文法や知識を身につけてほしいのである。そもそも、主観を交えずに読むことなど不可能で、もし意図的にそのように努めているとすれば、それは文章を読む楽しみを奪ってしまう。
多くの名文に触れ、たくさんの想いを馳せ、成長の糧としてほしい。文章を読む力は、あらゆる教科の礎であり、文章を読むことは、あらゆる学問への懸け橋となるのである。
SOCRAの英語
得点力=英語力×解答力。
点数アップにおいて必要な能力は、文法、単語、背景知識といった知識力、大意をとらえながら素早く読んだり、聞いたりできる情報処理能力といったいわゆる読解力(聴解力)、また、設問の意図を汲む理解力や問いに応じて情報を吟味する判断力といったいわゆる解答力からなる総体的なものです。
英語力向上のために・・・
reading(読む)、listening(聴く)、writing(書く)、 speaking(話す)の英語の4技能を各自の目標とする試験水準の語彙・文法ベースに応じて、万遍なく高めることを目標とします。ベースとなる語彙・文法のおいては早期着手が鍵となるため集中的に行います。インプットにおいては、正しく読めることから始め、読解スピードの向上、米国人のナチュラルスピードで速聴できるまでを目標とします。アウトプットにおいては、状況に応じた語法、正確な文法を駆使して表現できるように行います。
解答力向上のために・・・
単語や文法などの蓄えた知識の使い方を学ぶ必要があります。精読・精聴と多読・多聴をバランスよく行い、パラグラフ展開や各トピックの典型的論点を学び、初見の文章でも展開が予測できる状態を目指します。精読・精聴により英語の論理を学び、多読・多聴により英語を瞬間的に理解する力を磨きます。客観問題についてはパラフレーズなど典型的な仕掛けを学ぶところから初めます。記述問題については、問いに答えるための要件を理解し、それに応じて簡潔にまとめることを行います。
Reading
英語をリズムとして体得し、表現をイメージとして結び付けることで直観的に理解できる力を伸ばしながら、必要に応じて精読し、深く理解する力を育てます。解答力向上については、ボキャブラリーや文法などの蓄えた知識の使い方を学ぶ必要があります。問いに対して解答を導くまでの「どうして」にこだわり、リーズニング(理由づけ)を行います。各自の解答に対して、不正解問題については矛盾する箇所を示し、正解問題については合理的な判断基準を示すことで、英語で考える力を育てます。
Listening
聴解力向上については、精聴を通して、正しく音声を聞き取り、ダイアローグやアナウンスなど場面に応じた典型的なやり取りを覚えます。多聴を通して、何が話されるかの予測フレームを構築し、ある一定のまとまりを一時的に頭の中にストックしながら整理する力を育てます。解答力向上については、問いの意図を素早く理解する力、問いに応じて必要な情報を取捨選択し、判断する力が求められます。ボキャブラリーを増やしながら、音の変化やスピードにも対応できるよう、英語を聴いたままに理解できる力を育てます。
Writing
導入-演習-解説(添削)のサイクルで行います。知識を自在に運用し、自然な表現ができる状態を目指します。語法やコロケーションに着目し、書くために不自然でない単位に知識を細分化し、書くための「型」を学んでいきます。和文英訳では日本語との相違に留意し、細かいニュアンスを表現することを学びます。自由英作文では、パラグラフライティングにより、論理的に書く作法を学び、多様なテーマに対応するために、テーマ別に論点の整理を行います。
Vocabulary
各自学校で使用している単語帳を使用することができます。各出版社約20冊分の単語テストをご用意しております。毎週決められた分量にて、導入-暗記-テスト-解説のサイクルで行います。効果的に復習を繰り返し、効率よく知識の定着を図ります。単に意味を覚えるのではなく、各単語の語源、コロケーション、発音、使用場面などを学び、生きた知識を習得します。
使用単語帳例
ターゲット1900
「一語一義」主義を特徴とする単語帳です。過去5か年の最新の大学入試問題をコンピューターで徹底分析、よく出題される見出し語1900語を選び出し、それに対応する最も頻度の高い意味を掲載しています。
システム英単語
「ミニマムフレーズ主義」を特徴とする単語帳で、従来の単語帳と違い、入試でよくでるフレーズにて暗記するため、文法や英作文など語法を問われる場面で重宝する単語帳といえます。
速読英単語(必修編・上級編)
「単語力×速読力」を特徴とし、長文の中で単語を覚えます。それぞれの単語が使われる文脈を意識して覚えることができるため、単語の運用力を高めること期待できます。長文は実際の入試問題から抜粋しているため読解力の向上につながります。
英文和訳
英文和訳の鍛錬は、英文法、単語といった断片的知識を有機的に結び付け、読解という高次の行為へ橋渡しする役割を担います。単に英単語の日本語訳を5文型に従って当て嵌めるという機械的作業から脱し、日本語と英語との文構造の相違、概念的差異、トッピックにおける背景知識にまで踏み込み、英語と日本語が常に一対一対応でないことへ気付かせ、その差異を如何にして埋めていくかの注意を喚起し、日本語として自然な訳ができるように導きます。導入-演習-解説(添削)のサイクルで行います。添削によって、日本語としてより洗練された表現や国文法に忠実な構成を学びます。