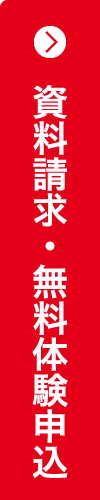英文法の大切さを考えてみよう
目まぐるしく変化を遂げる社会の中で、求められる人材モデルも変容し、
2020年「新学習指導要領の導入」「大学入試改革」「英語改革」の3つの教育改革が行われました。
そのうちの英語改革については、以下の通りです。
- 小学3・4年生での外国語活動の開始
- 小学5・6年生での教科としての英語導入
- 中学高校での授業の原則英語での実施
- 大学入試での4技能※評価の導入
※4技能:スピーキング、ライティング、リーディング、リスニング
このように英語教育の早期化とこれまでのインプット中心(リーディング、リスニング)から、発信型の技能が問われることとなります。この背景には、グローバル化が進む社会において「使える英語」の習得が要請されているところにあります。
上記4技能について考えるとき留意しておきたいこととして、それぞれの技能は独立したものでも、いずれかの技能が基礎となって他の技能が成立するといった垂直的な関係でもなく、4つの技能は本来相互に補完し合う関係であるということです。
ここでもう一つ注意しておきたいのが、4つの技能の水準を決定づける要素の存在です。それが知識力と思考力となります。では、知識力や思考力とはどのようなものでしょうか。知識力は、文法知識、語彙、背景知識、文章構成の型の理解といった思考する上での必要条件となる、いわば思考する上でのツールの多寡と考えられます。思考力は、これらの知識を、課題文や放送を理解するとき、問いに対して解答する上での条件整理をするとき、解答や意見としてまとめあげるときといった、場面に応じて運用できる力及びその瞬発力と考えられます。
今述べたことを前提として、表題にある「英文法の大切さ」とは何かを考えてみましょう。まず、文法力と一口に言いますが、3つの段階があります。以下の通りです。
- 文法知識として個々の項目を理解する段階。
- 文章理解や解答のために必要な知識を吟味し運用できる段階。
- 2のレベルを瞬時にできる段階
このように文法力には習熟度によって意味するところが変わってくるのです。また、1の段階では、知識としての理解にとどまるため「使える英語」を目標としたときには大きな隔たりがある状態です。ここから少しずつレベルをあげていく上で、ジャンルを問わずたくさんの英文や問題にあたることを通して、実際に文法の知識を使っていく経験を積んでいくことが必要ですが、折に触れて基本となるフレーズや文の理解や暗唱に努めることも大事になります。「できる」ことを増やすことと「わかる」ことを深めることのバランスを取りながら継続することが肝要となります。どのような英文も自分の立場に置き換えて接し、実際に使用する場面を想定して、自分なりに多少のアレンジを加えてみるといった能動的な姿勢が、生きた知識へと高めるコツではないかと思います。文法を正しく理解し、使いこなすレベルまで高める意識を持って取り組めば、具体的な成果として、
- 難解な英文も正確に理解できる
- 文章の展開に予測がつく
- 英文の組み立て方がわかるので、自分の考えたことを言葉にできる
- 解答の理由づけに自信が持てる etc.
といった、多くの利点があります。「使える英語」の修得が最終的な目標とはなりますが、その通過点としての受験英語を考える際、テストである以上点数がつくものである必要があることを踏まえると、正誤のはっきりするもので構成されていることがほとんどですので、その判断において、なんとなく読めた(聞けた)といった理解では太刀打ちできないのです。
文法の修得は、そうした曖昧さを排し、正確な理解と理路整然とした解答への道標となることは間違いありません。SOCRAの生徒の皆さんが、英語の4技能が意味するところを理解し、その達成のために必要な勉強を正しく積み重ねていってくれることを願ってやみません。
進学塾SOCRA&jr.
一流中・医学部・東大受験指導科
大熊 将吾