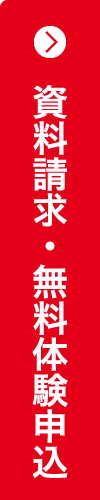体系数学の学び方
まずは体系数学から始めよう!
体系数学シリーズは中高6ヵ年の内容を学習指導要領にとらわれない体系的な配列で再編成した教材です。例えば中学1年生で習う「方程式」と高校1年生が習う「不等式」は自然につながる内容であり、体系数学では「方程式」の後に「不等式」を学ぶカリキュラムとなっています。そのような多くの中高一貫校で採用されており、昔から算数数学の勉強をしていて数学がずば抜けて得意、という方以外は中学段階においてはまずこの体系数学を学べば大学入試に向けた中学段階の数学の理解としては十分です。この長期休みに、より一段数学の力をつけるための体系数学の学び方をお伝えします。
体系数学を制するものが中学数学を制する!
体系数学では基本的な事項や問題が教科書にまとめられており、体系問題集で演習することにより力がつきます。体系問題集はLevel A, B(と部分的にC)と難易度別に問題が分かれていて、基本に不安のある人はLevel Aを確実になるまで反復しましょう。「Level A」=「簡単」というわけではないのです。学校の定期テストでもLevel Aの問題が出てくる割合は高く、数学が苦手だと感じる人はLevel Aを確実にするだけで理解度や得点力はかなり上がると思います。ただし、さらなる高みや定期テストで高得点を望むためにはLevel Bの問題の理解も不可欠になります。Level Bの問題は難易度が高く、一朝一夕でできるものではないです。そのため、Level Bをこれから頑張りたいという方には、以前に習った単元のLevel Bに挑んでみることをお勧めします。長期休みは過去の振り返りをする絶好のチャンスです。逆に言えば、通学しながらの学習は今やっている分野に追われてしまうため、復習をするのは難しいと思います。「体系数学さえやれば大丈夫」と信じてこの長期休みを体系数学に注ぎましょう。
チャート式体系数学も見てみよう
体系数学シリーズには「チャート式体系数学」という参考書があります。体系問題集に載っている問題の中で基本的なものや重要なものについて、例題を通して解法が詳しく解説されています。体系問題集で分からない問題がある時は、チャート式で似た問題を解いてみましょう。実はチャート式は高校数学では標準的な参考書であり、大学受験まで続くものです。今からチャート式を通した勉強に慣れておくと将来有益でしょう。
体系数学は中学の参考書だけでは足りない!?高校の参考書も見てみよう!
体系数学は前述の通り、中学の内容だけでなく高校の内容も含まれます。中学の参考書を手に取ってしまうかもしれませんが、調べたい・練習したい項目が載っていないことが多々あります。そんな時は高校の参考書を見てみると役立つ情報や問題・解法が載っているということがあるのです。ただし、自分で参考書を調べたり有用なところを抜き出したりするのはとても難しく、時間がかかることです。ぜひソクラの先生に相談してもらい、効率よく勉強するようにしましょう。
進学塾SOCRA&jr.
一流中・医学部・東大受験指導科
山下 慎司